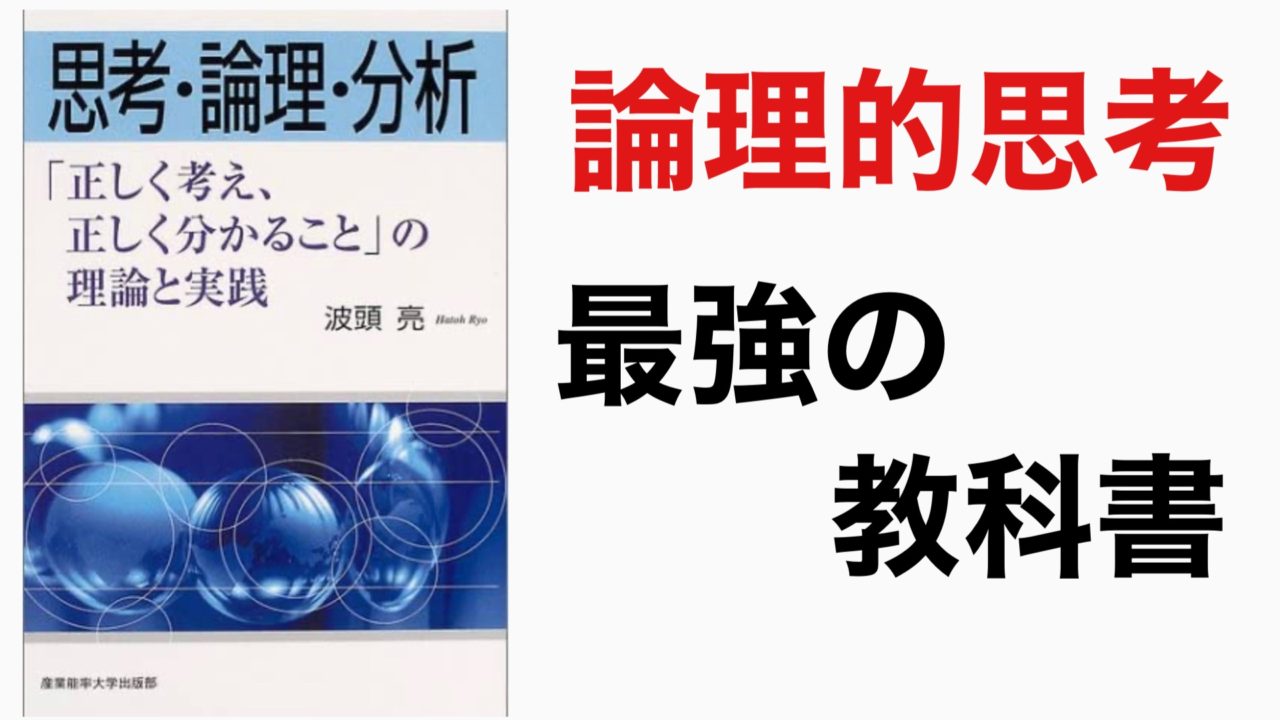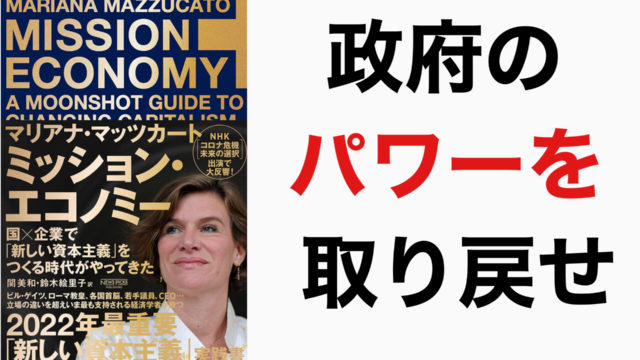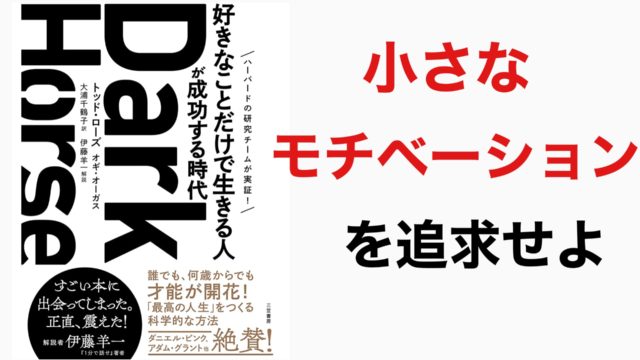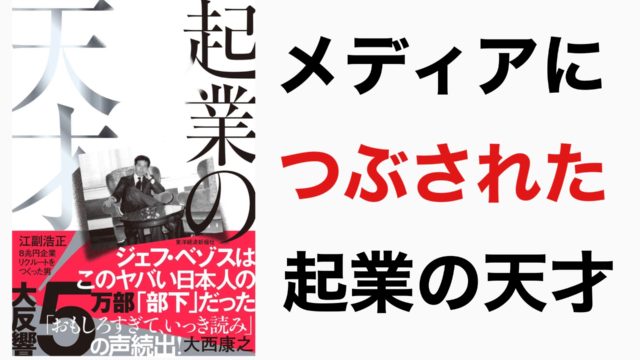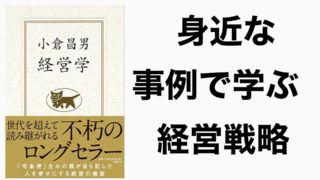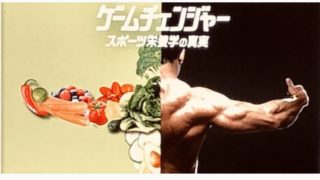今回紹介する本は、「思考・論理・分析―『正しく考え、正しく分かること』の理論と実践」です。
この本の著者は、元マッキンゼーで経営関連の書籍を多数書いている波頭亮氏です。最近ではNewsPicksの動画なんかにもよく出演しています。
この本は、コンサルタントのみならず全ビジネスマンに必要な論理的思考について書かれた本です。
ちまたの論理的思考に関する本は、ただフレームワークを紹介するハウツー本が多い中、この本は「そもそも思考とはなんぞや」という本質的な話から説明してくれるので、最終的な目的である「論理的思考」や「分析」に関する話の理解度がかなり上がります。
いろいろと論理的思考に関する本を読んできましたが、この本が論理的思考の最強の教科書です。
なので、「フレームワークは一応知っているけど、もっと本質的な論理的思考法を身につけたい」という人におすすめの本です。
そもそも思考とは?
「低いうなり声をあげている、黒い毛に覆われた、軽自動車ぐらいの大きさの動物」
と言われてあなたはなにを思い浮かべるでしょうか?
きっと、こんな感じで考えるのではないでしょうか?
①低いうなり声をあげている⇒犬、ライオン、トラ、ヒグマあたりがありえるかな?
②黒い毛に覆われている⇒犬はありえる、ライオンは違う、トラは違う、ヒグマはありえる
③軽自動車ほどの大きさ⇒犬は違う、ヒグマはありえる
あっ、ヒグマだ!
このように、得られた情報と自分が持っている知識を比較して、どこが「同じ」で、どこが「違う」かを考えることでヒグマという答えにたどりつくことができます。
これがまさに思考なのです。
つまり、思考とは「思考対象に関してなんらかの意味合いを得るために、頭の中で情報と知識を比較して同じ部分と違う部分に分けること」なのです。
上司から「よく考えろ!」と言われることはあっても、「どう考えるか」について教えてもらうことってないですよね?私は、この定義を読んで「考える」ってそういうことだったのかと衝撃が走りました。
「同じ」と「違う」を分けることが、考えることの核心だったのです。
正しい分け方とは?
「同じ」と「違う」を分けることが、考えることの核心なのですが、この「分け方」が思考をする上でのポイントになります。
では、正しく分けるにはどうしたらいいのでしょうか?
それは、以下の3点に気を付けることです。
- ディメンション(抽象度)
- クライテリア(分類基準)
- MECE(モレなくダブりなく)
ディメンション
最初に、ディメンションについて説明します。
ディメンションとは抽象度のことを表します。この抽象度を統一することが正しく分けることのポイントになります。なぜなら、分けて比べるためには、まず比較しようとしている要素が同じ抽象度でなければ、比較できないからです。
例えば、「野菜とリンゴはどちらが好きですか?」と聞かれたら違和感を感じないでしょうか?
この違和感は、野菜とリンゴでは比較対象として抽象度が揃っていないことから発生しています。抽象度が揃っていないと比較することが難しくなるのです。
クライテリア
次に、クライテリアについてです。
クライテリアとは、思考対象を分類する切り口、つまり分類基準のことです。
例えば、食べ物は素材の種類で分ければ「魚料理、肉料理、卵料理・・・」などに分けられますが、料理の国籍で分ければ「和食、フランス料理、イタリア料理、中華料理・・・」という具合にも分けられます。
この分類基準がクライテリアです。
正しく分けるということは、適切なクライテリアを選択できるかということと同じ意味になります。様々なクライテリアを持っておくことが、正しく分けるために重要になってきます。
MECE
最後に、MECEです。
これは、論理的思考の本には必ず出てくる考え方で、モレがなくダブりもない状態を表します。
例えば、人間を血液型で分ける場合は、A型、B型、O型、AB型と分ければ、MECEです。もしAB型が抜けていれば、モレがある状態です。
つまり、正しく分けられた状態=MECEとなります。
この3点に注意をして、正しい分け方ができるようになれば、思考の質も上がります。
この思考の話が1章なのですか、2章以降では、思考の話をベースに、論理的思考の本質について解説しています。
本質的な論理的思考法を身につけたいという人は、是非読んでみてください。